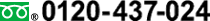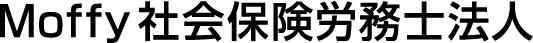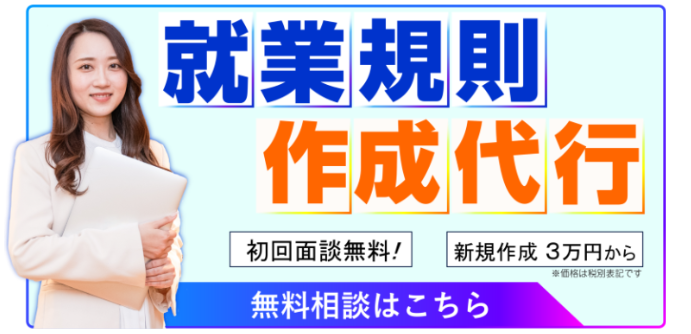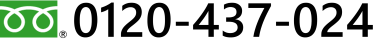- お役立ちコラム
就業規則の作成義務とは?作成・届出しないとどうなる?
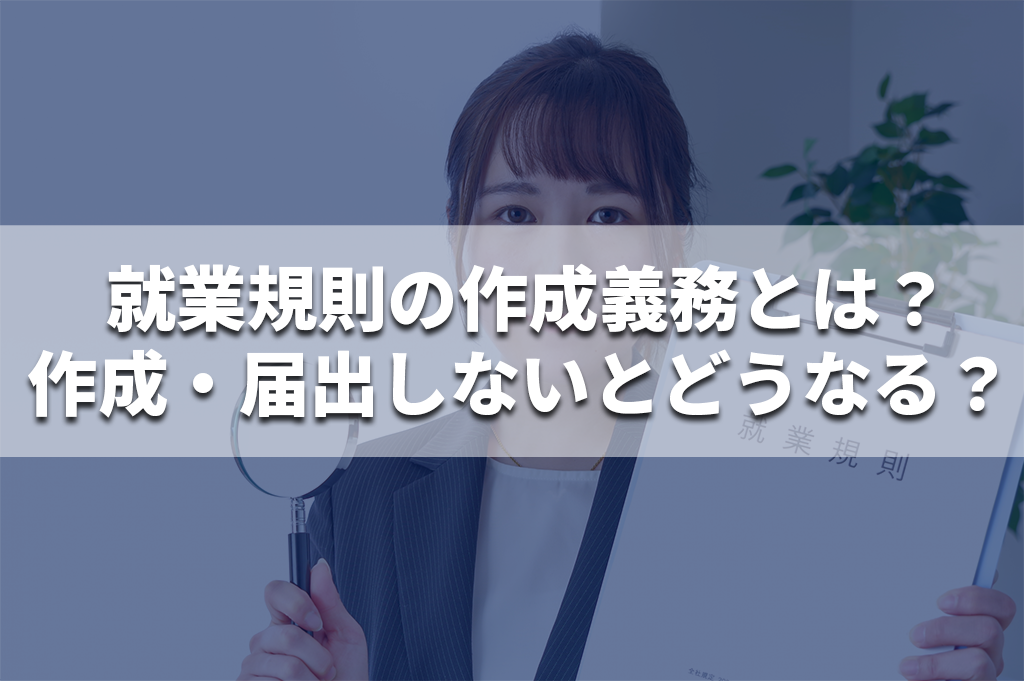
目次
はじめに
「うちの会社、就業規則って作らなきゃいけないの?」
従業員が増えてきたとき、あるいは人事トラブルや労務整備の必要性が高まったとき、こんな疑問を持つ方は少なくありません。
実は、一定の条件を満たす会社には、就業規則の「作成義務」や「届出義務」が法律で定められています。そしてこの義務を怠ると、行政指導や罰則、最悪の場合は企業名が公表されるリスクもあるのです。
本記事では、就業規則の作成義務とは何か、どんな会社に適用されるのか、作らなかったり届出をしなかったりした場合にどのような不利益があるのかを、法律の根拠と実例を交えて分かりやすく解説します。
「作るべきかどうか」だけでなく、「いつまでに、どうすべきか」も理解できる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
就業規則には作成義務がある!
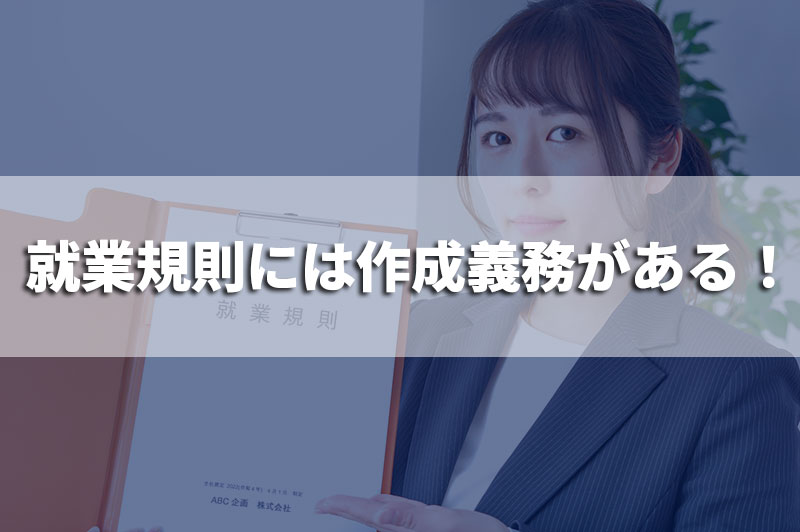
まずは、「なぜ作成義務があるのか」「誰が・いつ・どの法律で決めたのか」、そして「就業規則制定の目的」といった根幹部分を押さえましょう。
-
- なぜ作成義務があるのか?
就業規則を明文化することで、労働時間、休日、賃金、解雇理由などの労働条件を明確にし、労使間のトラブルを未然に防止します。法的に整備されたルールがあることで、企業と従業員双方が安心して働ける環境が構築されます。
- なぜ作成義務があるのか?
-
- 誰が・いつ・どの法律で定めたのか?
1947年に制定された「労働基準法」(昭和22年法第49号)によって定められ、厚生労働省の前身が主導して制定。戦後、労働者の権利保護と職場秩序を確立する目的で導入されました。
- 誰が・いつ・どの法律で定めたのか?
-
- 該当する法律と条文
以下が、就業規則に関する主な法的根拠です。
労働基準法 第89条(就業規則の作成および届出義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出なければならない
- 該当する法律と条文
-
- 就業規則制定の目的とは?
目的 内容 労働条件の明確化 賃金、労働時間、休暇などを明記し、認識ズレを防止 労使トラブルの未然防止 解雇や懲戒、残業などで争いを回避 職場秩序の維持 服務規律や安全衛生の基準を提示 法令遵守の徹底 労働法令と整合する制度構築 従業員の安心感 ルールが明示されることで安心して働ける 経営安定・採用への影響 信頼ある企業イメージ形成につながる このように、就業規則は単なる事務的な書類ではなく、企業と従業員の信頼関係構築や、法令遵守を前提とした制度設計の土台でもあります。
- 就業規則制定の目的とは?
就業規則の作成義務が生じるケース
就業規則の作成義務は、「常時10人以上の労働者」を使用する事業場に課されます(労働基準法第89条)。
ここでの「10人」は、正社員だけでなく、雇用契約が継続している労働者すべてを指します。
-
- 数え方の基本と注意点
雇用形態 カウント対象 補足 正社員 ○ 常時雇用されていれば全員対象 パート・アルバイト ○ 労働時間や日数に関係なく、雇用契約があれば対象 契約社員(有期雇用) ○ 雇用契約期間中は対象 育児休業・産休中の社員 ○ 雇用契約が継続していればカウント 長期病気休職中の社員 ○ 解雇等されていなければ対象 役員 △ 役員はNG、使用人兼務役員はカウント 派遣社員(受入側企業) × 派遣元でカウントされるため対象外 登録だけされている超短期勤務者 △ 実態として雇用継続がなければ対象外になることも 定年退職予定者・死亡した社員 × 在籍していなければ対象外 グループ会社で兼務している社員 △ 就業場所ごとの事業場単位でカウントされる
- 数え方の基本と注意点
-
- イレギュラーな例の仮定と考え方
・年に数日しか働かない登録制パート:
→雇用契約があり、事実上の継続雇用と認められるなら対象。
→臨時的に使用する有期雇用者は常時使用する労働者には含まれません。・グループ企業での兼務:
→それぞれの事業場でカウントする場合
A事業所とB事業所を兼務している従業員がいる場合、A事業所の人数に1名、B事業所の人数に1名としてカウントします。→出向・在籍出向の場合:
雇用契約を結んでいる元の会社(出向元)にカウントされます。出向先の会社ではカウントしません。・育児休業中の社員が複数名いる:
→復帰予定があれば、休業中でもカウントされる。
→介護休業や、休職中の人もカウントされます。
- イレギュラーな例の仮定と考え方
-
- 判断に迷ったら
「常時10人以上」かどうかの判断は、単なる人数ではなく「継続的な雇用実態」に基づきます。一時的な増員や登録のみの人材は対象外とされることもあるため、迷ったら専門家か労基署に相談するのが確実です。
- 判断に迷ったら
就業規則の作成義務が生じないケース
就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用している場合に限られます。
そのため、従業員が常時9人以下の事業場には、法的な義務はありません(労働基準法第89条)。ただし、義務がない=不要というわけではありません。10人未満の会社であっても、トラブルを未然に防ぐために就業規則を作成するメリットは大きいです。
-
- 作成義務がない理由と背景
労働基準法は、規模の小さい企業の負担を軽減する観点から、義務の対象を「常時10人以上」に限定しています。
しかし近年は、労働条件や働き方に関するトラブルが増加しており、従業員の規模に関係なくルールの明文化が求められる時代です。
作成義務がない状況においても、トラブルを未然に防ぐために就業規則を作成することをおすすめします。
- 作成義務がない理由と背景
複数の事業所(営業所、支店等)がある場合は?
作成義務と届出義務に関する従業員数は、1事業所あたりの労働者をカウントします。仮に会社全体の労働者数が10人を超えていても、1事業所あたりの労働者が10人未満であれば、義務は発生しません。
A事業場は10人以上、B事業場は10人未満の場合の場合、B事業場については、作成義務や届出義務はありませんが、同一企業であれば、同一のルールで運用したほうが、会社全体として最適な運営が可能となります。本社にて一括して就業規則の作成を行い、届出を行うことも可能ですので、同じルールを作成したほうが良いでしょう。
就業規則は作成義務に加えて、届出義務もある!
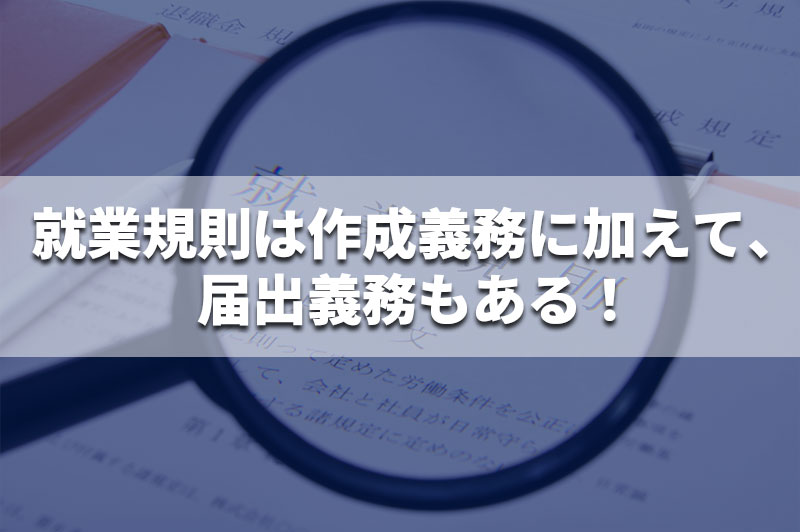
就業規則は、作成するだけでは不十分です。労働基準法第89条により、「常時10人以上の労働者」がいる事業場では、所轄の労働基準監督署への届出も義務付けられています。
届出をしないまま運用を始めると、法的には「未届出」と見なされ、是正勧告や罰金の対象になることがあります。
-
- 届出義務の時期と必要書類
就業規則の作成または変更から速やかに、以下の書類を添えて届出る必要があります。
・就業規則本体
・労働者過半数代表の意見書(労働基準法第90条)届出書と意見書のWordファイルは、以下のページからダウンロード可能
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/dl/25.docx
- 届出義務の時期と必要書類
就業規則の作成方法
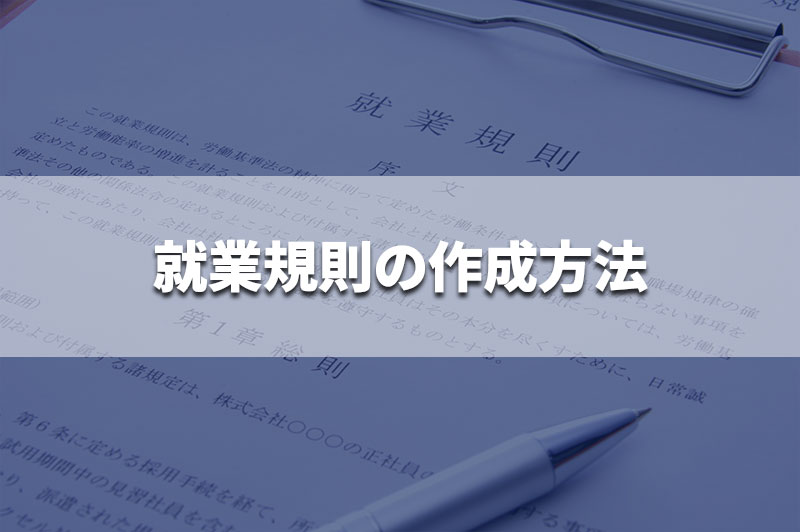
就業規則を作成するには、労働基準法などの関連法令を踏まえながら、自社の実情に即した労働条件や社内ルールを文書化する必要があります。
作成手順(基本の流れ)
1.現状の労働条件・制度を整理
2.就業規則のひな形(厚労省など)を参考に文案を作成
3.法令違反がないかチェック
4.労働者代表の意見聴取(労基法第90条)
5.労働基準監督署に届出
-
- 就業規則制定の目的とは?
内容 概算 作成期間 約2週間〜1か月(自作の場合) 作成コスト 自作=無料、社労士依頼=5〜20万円程度
- 就業規則制定の目的とは?
-
- 必要な知識・資格
作成自体に資格は不要ですが、労働基準法、パートタイム・有期法、育児介護休業法などの正確な理解が必要です。
自社での作成に不安がある場合は、社会保険労務士への外注が有効です。
- 必要な知識・資格
-
- 外注のメリット(例)
・法改正や判例動向を踏まえた内容にできる
・リスクの見落としを防げる
・スムーズに労基署対応まで任せられる
- 外注のメリット(例)
就業規則の届出方法
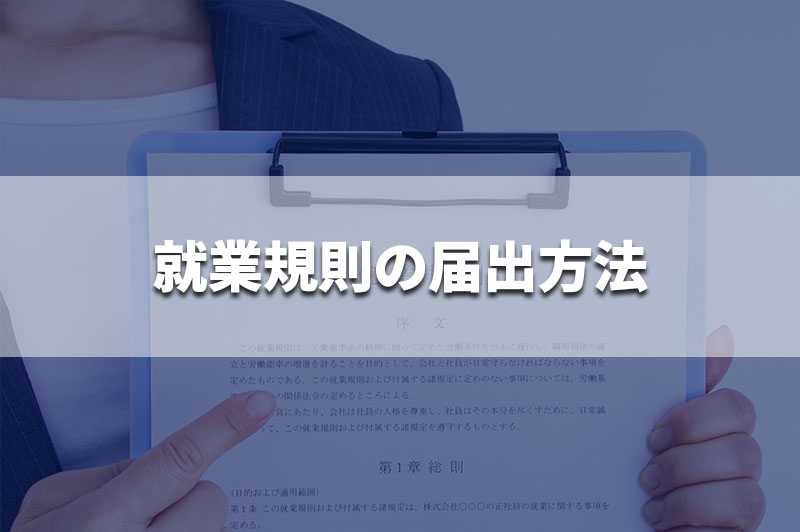
届出には、以下の書類が必要です。これらを「2部」づつ準備しましょう。「1部」は提出用。もう「一部」は自社の控えで労働基準監督署の受領印をもらった上で保管しましょう。
・就業規則(賃金規程、育児介護規程等、作成したすべての規程)
・意見書(労働者の過半数代表者が署名または記名押印)
・届出書(就業規則(変更)届)
-
- 届出の期限・方法
就業規則の作成義務に関するよくある質問
Q1.就業規則の作成義務は、従業員が何人から発生しますか?
A.労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成と届出が義務付けられています。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員もカウント対象です。
Q2.パートやアルバイトも「常時10人」に含めて数えるのですか?
A.はい、含まれます。就業規則の作成義務における人数カウントは、雇用形態に関係ありません。
常時使用しているかどうかが基準となるため、パートや短時間労働者も要注意です。
Q3.事業場単位で従業員が10人を超えた場合のみ義務があるのですか?
A.その通りです。就業規則の作成義務は「会社単位」ではなく「事業場単位」で判断します。支店や営業所ごとに10人を超えたかどうかを確認してください。
Q4.育児休業中・休職中の社員もカウントすべきですか?
A.はい。雇用契約が継続している社員は「常時使用する労働者」としてカウントされます。たとえ一時的に出勤していなくても、人数に含めて就業規則の作成義務を判断します。
Q5.派遣社員は「常時使用する労働者」に含めますか?
A.派遣元の企業の労働者であるため、派遣先ではカウントしません。ただし、契約形態によって判断が難しい場合は、専門家への相談が確実です。
Q6.就業規則は作成するだけでいいのですか?届出義務もあると聞きました。
A.作成だけでなく、所轄の労働基準監督署へ届出る義務(労働基準法第89条)があります。併せて「労働者代表の意見書」を添付(労働基準法第90条)する必要があります。
Q7.就業規則の届出をしなかった場合、罰則はありますか?
A.はい。労働基準法第120条により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。行政指導・是正勧告を受ける前に、速やかに届出しましょう。
Q8.就業規則の作成や届出は、自社でできますか?外部に依頼する必要は?
A.自社作成も可能ですが、法改正や判例に対応するには専門知識が必要です。特にトラブル防止やリスク回避のためには、社会保険労務士に就業規則の作成・届出を依頼するのが安心です。
Q9.就業規則の作成義務があるのに、まだ作っていません。今からでも間に合いますか?
A.はい。義務が生じている以上、早急に作成・提出を行うことが求められます。過去の不備を是正するためにも、早めに社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
Q10.就業規則を作成したら、労働者全員に説明・周知する必要がありますか?
A.はい。就業規則の効力を持たせるには、労働者への「周知」が法的に必須です。印刷して事業場に掲示する、イントラネットに掲載する、配布するなどの方法が必要です。
就業規則の作成義務や届出義務に不安がある方は、専門家に相談するのが最も確実な方法です。
就業規則の相談はACCS社会保険労務士法人まで!
・「誰をカウントすべきかが曖昧」
・「法改正に合っているか不安」
・「ひな形で作ったけど、これで本当にいいのか?」
・「忙しくて、手が回らない……」
このような悩みを抱える方は多く、制度としての就業規則は「書いて出せば終わり」ではありません。法律と現場運用の両方を理解して、初めて「意味のある就業規則」になります。
不安なまま放置するより、専門家に相談するという選択を
私たちACCS社会保険労務士法人では、法令に準拠した就業規則の作成・見直し・届出をトータルサポートしています。
会社ごとの事情に応じて、形式だけでなく実際に使える規則を提案することが可能です。
「これで大丈夫」と言い切れる安心感を得るためにも、まずはお気軽にご相談ください。